日本アドラー心理学振興会 認定心理療法士、認定心理カウンセラーの田中詠二こと、えいさんです! 子育て、仕事、人間関係の悩みに、心理学の観点から解決のヒントをお届けします。
「叱る」という行為は、実は“火に油”かもしれない
子どもが、何度注意しても言うことを聞かない。 部下が、同じようなミスを繰り返してしまう。
そんな時、私たちは「教えなければ」「正さなければ」という思いから、つい、相手を「叱って」しまいます。それは、相手のためを思っての、愛情や善意からくる行動のはず。
でも、アドラー心理学の視点に立つと、その「叱る」という行為こそが、問題をさらに悪化させている可能性がある、と考えるのです。
なぜ、叱っても効果がないのか?
叱るという行為は、相手に「あなたが間違っている」「私の言うことを聞きなさい」と伝える、典型的な「縦の関係」のコミュニケーションです。
自分より上の立場から、一方的に「正しさ」を押し付けられた相手は、どう感じるでしょうか? 素直に「わかりました、改めます」となるでしょうか。
多くの場合、相手は「反発」するか、あるいは「萎縮」してしまいます。 そして、もっと厄介なのは、叱られること自体が、相手の「目的」になっている場合があることです。
例えば、親に構ってもらえない子どもは、いたずらをして叱られることで、親の注目を自分に引きつけようとします。 そう、その子にとって、叱られることは「自分に関心を向けてもらえた」という、ある種のご褒美になってしまうのです。 これでは、叱れば叱るほど、問題行動は強化されてしまいます。
雑草を抜くより、花を育てる
では、私たちはどうすればいいのでしょうか。 そのヒントは、「問題行動に注目するのをやめ、適切な行動に注目する」ことです。
アドラー心理学の師である野田俊作先生は、こう言います。 「雑草は抜けば抜くほど生えてくる。そんな暇があったら、いいものをたくさん育てる。そのいいものの力で悪いものが消えてしまいますから」
問題行動という「雑草」を一つひとつ見つけては、叱って抜き取ることにエネルギーを費やすのではありません。 相手がしてくれた、ごく当たり前の「良いこと」に光を当てるのです。
- 「おはよう」と挨拶してくれたら、「気持ちのいい挨拶をありがとう、嬉しいな」と伝える。
- 食事の後、お皿を運んでくれたら、「助かったよ、ありがとう」と感謝する。
これが、評価や支配ではない、「横の関係」に基づいた「勇気づけ」です。 「自分は役に立てるんだ」「ここにいていいんだ」という貢献感と所属感を感じた人は、自ら適切な行動を選ぶようになります。
あなたが誰かとの関係で、同じことを繰り返し叱っているとしたら。 一度、その人の「雑草」を見るのをやめて、その人の中に咲いている、小さな「花」を探してみませんか。 その花に、感謝と喜びの水を注ぐこと。それが、お互いの関係を健やかに育む、何よりの方法なのです。
もし、どうしても相手の「雑草」ばかりが目についてしまうなら、ぜひご相談ください。 カウンセリングは、あなたの見方を変え、相手の中に眠るたくさんの「花」を見つけるお手伝いをする場所です。
初回カウンセリング(オンライン)はこちらからお申し込みいただけます。
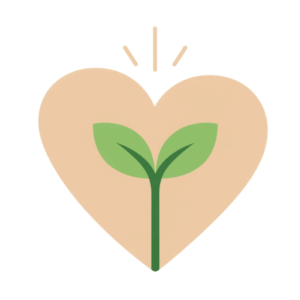
お会いできるのを楽しみにしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 LINE公式アカウントでは、今後も皆さんの日々の悩みに役立つヒントを配信していきます。ぜひ、友だち追加をしてくださいね。



コメント